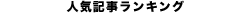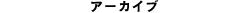今日から早くも5月1日。5月は風薫る季節で、暦上はすでに初夏です。GW中はどうぞ緑の中を散策してください。
ところで、この間のトマ・ピケティの『21世紀の資本』の勉強会でも明らかになったように、彼の学問的功績の第一は、富と所得に関するぼう大な歴史的データを提示したことにあります。このことにより、21世紀は19世紀資本主義と同じく不可避的に格差を生み出す、ということを歴史的に証明しました。この結果「資本主義が発達すれば(所得)格差は自動的に縮小する」とする主流派経済学の超楽観論は打ち砕かれました。
さて、データ=事実の集積は、なまなかな理論や仮説、ましてイデオロギーを吹き飛ばすくらい威力があるものですが、次のデータはいかがでしょうか。何かしら暗澹たる感慨をもたらすものですが。
それは「親の収入が多いほど、子どもの脳は発達する」というものです(逆に言えば、貧困下に育った子どもの脳は未発達に留まる)。下記のレポートをお読みください。
●米国で実証された「金持ちの子供は頭がいい」 年収300万円の家の子は、富裕層の子より大脳皮質が6%小さかった
簡単に要旨を記すと、ロサンゼルス小児科病院とニューヨーク・コロンビア大学医学部を含む9大学の研究者25人が、3歳から20歳までの1099人の子どもの脳の高解像度のMRIによる画像解析と両親・家庭の社会経済学的要因の聞き取り調査を行い、結果は世帯年収が2万5000ドル(約300万円)未満の家庭に育った子供たちは、15万ドル(約1800万円)以上の家庭の子供たちよりも、MRIの計測値で大脳皮質の領域が6%小さかった、というもの。
ここでの大脳皮質の領域というのは、とくに言語と認識力をつかさどる脳の部位であり、ここに親の収入によって差異が生じているというのですが、同研究の筆頭執筆者は「生まれ持った資質よりも世帯年収の差違の方が学力に影響を与える」と言っているそうです。
もちろん貧困家庭に生まれても(大脳皮質が小さくても?)勉強ができる子どもは必ずいますが(レポーターの堀田氏はこちらの方の神経科学的・社会経済学的な要因を探ってほしいと言っているが)、残念ながらそれは圧倒的に小数であるのも現実です。そういう意味では何ともやり切れないものがありますが、大脳皮質の大小(発達度)も貧困と格差に関係があるのかもしれません。
ところで、以下の記事は昨年のハフィントンポストに載ったものですが、富裕層と貧困層の格差が一目瞭然です。米国、北朝鮮、シリア、18世紀のフランス、古代ローマの「持てる者と持たざる者」の食事です。
●富裕層と貧困層の食事を並べてみた 「持てる者と持たざる者」の目に余る格差(画像)
◆中の写真は、ハフィントンポスト電子版より