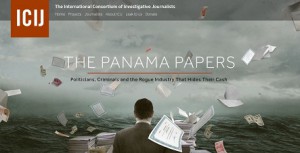グローバル連帯税フォーラムは、本日の「パナマ文書」の全ファイルの公表にあたり、以下のようにプレスリリースを行いました。
報道関係各位
「パナマ文書」の徹底究明、公正な国際課税制度の実現を
・タックスヘイブンに関する情報の公開
・違法な脱税の摘発、処罰
・グローバル企業情報の公開
・タックスヘイブン規制の強化
・伊勢志摩サミットでの国際連携における主導性の発揮
本日未明、「国際調査報道ジャーナリスト連合」(ICIJ)は「パナマ文書」に登場する21万余の法人(ペーパーカンパニー)とその株主らの名前をウェッブサイトで公表しました。このペーパーカンパニーに関係している日本在住の個人と日本企業は合わせて約400を超えており、東証一部上場企業や著名な企業経営者の名前も含まれています。
これら大企業や富裕層がタックスヘイブンを利用するのは、節税・脱税などを行って税金を逃れるためです。こうした行為により世界的に見れば、法人関係で1000億~2400億ドル(11兆円~26.4兆円)の税収の逸失を、個人関係で1900億ドル(21兆円)の税収の逸失をもたらしています。つまり、世界的には50兆円もの巨額なお金が税金として納められず、大企業や富裕層のふところに入っているのです。
これは明らかに税制の公正さを欠くものであり、国や自治体の成り立ちを危うくするものです。一言でいえば民主主義の危機です。
このような観点から、当グローバル連帯税フォーラムは日本政府・財務省に対して、別紙のような「『パナマ文書』の徹底究明、公正な国際課税制度の実現を」とする要請書を提出する予定です。その上で、私たちは航空券連帯税や金融取引税などのグローバル連帯税の実現とともに、脱税やマネーロンダリングの温床となっているタックスヘイブンを廃絶するために活動していく所存です。
●問合せ先:グローバル連帯税フォーラム事務局(担当:田中)
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-20-6 丸幸ビル3F
Tel: 03-3831-4993 Fax: 03-3834-2406
「パナマ文書」の徹底究明、公正な国際課税制度の実現を要請します
財務大臣 麻生太郎 様
グローバル連帯税フォーラム
代表理事 金子文夫、田中徹二
2016年4月~5月に公表されたいわゆる「パナマ文書」は、世界の富豪、大企業がタックスヘイブンを利用して「合法的脱税」を行っている実態を明らかにし、世界に衝撃を与えました。世界の人口の1%にすぎない富裕層が世界の資産の50%を保有しているといわれるように、世界的な冨の偏在は著しくなってきており、タックスヘイブンはこうした格差を広げる役割をもっています。タックスヘイブン・システムのもとで、世界全体で年間法人税収の逸失は1000億~2400億ドル(11兆円~26.4兆円)、すなわち世界の法人税収の4~10%にも上り、また個人資産への税収の逸失は1900億ドル(21兆円)にも上るという推計もあります。
このような不公正な税のあり方を是正するために国際社会は一致して取り組むべきですが、「パナマ文書」は、あろうことかイギリス、ロシア、中国などの最高権力者・関係者が不正な蓄財、租税回避に関与した事実を暴露し、人々の強い怒りを呼んでいます。今こそ格差是正、税の公平性の実現、財政健全化のために、国際課税制度の抜本的な改革を進めるときです。
すでに4年前にOECD租税委員会は、グローバル企業の目に余る租税回避行動に対処するために、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを発足させ、2015年10月に「最終報告書」を公表しました。そこには、グローバル企業の世界的な活動の報告義務、租税回避の防止策など、多くの評価すべき勧告が盛り込まれています。
私たちは、「パナマ文書」の徹底究明とともに、BEPS報告書の積極的内容を活かした公正な国際課税制度の実現のために、日本政府に以下の5項目の実施を要請します。
記
1.タックスヘイブンに関する情報の公開
「パナマ文書」その他の資料を使ってタックスヘイブンに関する実態調査を行い、タックスヘイブンを利用している個人名、企業名をすべて公表し、真の所有者を特定すること。
2.違法な脱税の摘発、処罰
現行の法制度に違反し、必要な税務処理を行っていない個人、企業に対して漏れなく査察を行い、厳正に処罰すること。
3.グローバル企業情報の公開
今後整備される金融情報の自動交換制度や多国籍企業の国別報告制度を通じて収集した情報を公開すること。これらの制度にはタックスヘイブンを含むあらゆる国・地域を例外なく参加させること。とくに後者にあっては、4月12日提案された欧州員会の“大企業の税逃れを防ぐ制度”を参考に徹底した情報公開と透明性を図ること。
4.タックスヘイブン規制の強化
情報交換に応じないなど、公正な税制の実現を妨げるタックスヘイブンを廃絶していくために、そのようなタックスヘイブンとのあらゆる取引を禁止すること(そのタックスヘイブンの中に米国のデラウェア州やワイオミング州なども含まれる)。
5.国際連携における主導性の発揮
G7伊勢志摩サミットで租税回避問題の解決に向けて主導性を発揮するとともに、開発途上国を含むより広範な国々が対等の立場で参加することのできる国際的枠組みの形成を目指すこと。
以上