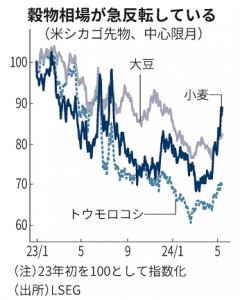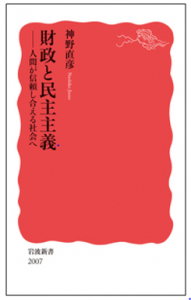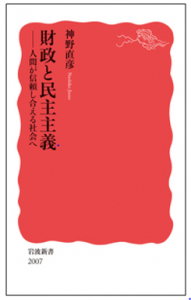
峰崎直樹さんの『チャランケ通信』を送ります。峰崎さんは、このブログで何回か紹介しましたように、民主党政権時代に財務副大臣を務め(2009年~10年、12年までは内閣参与)、政府税制調査会の責任者でもありました。また、国際連帯税に関してよき理解者でもありましたので、税制調査会の専門家委員会(委員長が神野直彦先生)の下に国際連帯税を含む国際課税小委員会を設置されるなど、国際連帯税を実現すべく準備をなされました。
2010年9月6日に開催された小委員会の第1回目会合には租税法学会の権威である金子宏先生(当時、東京大学名誉教授)が国際人道税に関する特別報告を行うなど、連帯税実現に向けてのお膳立てが進められていました。ところが、何と!当時ナショナルフラッグである日本航空が倒産し(負債2.3兆円ほど)、さらに、全日空も史上最悪の赤字を出すなど航空業界を取り巻く環境がたいへんに厳しく、結果として航空券連帯税導入は実現に至りませんでした。以下、チャランケ通信です。
チャランケ通信 第515号 2024年4月8日
峰崎 直樹
■ 神野直彦著『財政と民主主義』(岩波新書2024年2月刊)を読んで
2月中旬の頃、神野直彦東大名誉教授から『財政と民主主義』という岩波新書を送っていただいた。この本は、最近の新書販売ランキングの中でもベストテンに入っていたようで、社会科学系の本にしては比較的多くの人に読まれている。
私もこの本は、是非とも多くの国民に読んで欲しいと思う好著であり、網膜剥離という眼の病に侵され、失明の危機を乗り越えられながらご家族やお弟子さんたちの温かいご支援を得、苦闘されてきた著者の憂国の思いが全面展開されていて読む者にその思いが迫ってくる。特に私が望みたいのは、財政を論議し民主主義のアリーナで日々格闘されている各級議員や首長の皆さん方には、是非とも読んで欲しいと思う。
■ 神野先生との出会い、「地方消費税」新設の提案に感激
私が最初に神野先生とお会いしたのは、1994年頃だったと記憶する。当時「自社さ連立による村山政権」の時代で、当選後2年、まだ1期生の若造でありながら与党税制決定会合の一員として消費税3%から5%への引き上げに直面していた。そんな消費税増税議論が展開されていた時、参議院議員会館の私の部屋に自治省(当時)の税制担当課長であり後に総務省事務次官から民主党政権の内閣官房副長官となられた滝野欣弥さんとご一緒に訪ねてこられ、地方消費税(新設)の必要性について熱心にお話しされたことを思い出す。
引き上げ分2%の内1%を新しく地方消費税にするというのはなかなか大変な事だったが、地方財政の独自財源強化は自治体労働運動に従事してきた私にとっては魅力のある提言だった。結果、この税制改正で1%が地方消費税となって実現できた事を、主として税を担当した者の一人として、一つのレガシィとして忘れることはできない。
■ 自社さ政権時代に消費税5%への増税、村山総理、五十嵐官房長官にも恵まれ、地方消費税で何とか乗り切れたのでは
1989年に消費税の導入した直後の参議院選挙で、当時の社会党が大勝利し、土井たか子委員長が「山が動いた」と高らかにその勝利を宣言されてまだ5年しか経過しておらず、当時の参議院社会党の大半の議員は消費税に反対して当選してきたわけで、なかなか消費税の引き上げには抵抗が強かったことは確かであった。
それだけに、地方消費税の導入という提案は、地方分権・地方自治の強化という観点から何とか理解を得ることができ、総理大臣が自治労出身の村山富市さんで官房長官が元旭川市長の五十嵐広三さんであったこともあり、社会党も辛うじて消費税引き上げに賛成へと舵を切ることができたのだ。
■ 民主党菅総理、神野理論「強い経済、強い財政、強い社会保障」で武装
その時、理論的な支えとなったのが神野直彦先生であり、以降税財政問題についての導きの星として民主党政権時代には大変な役割を果たしていただいたことが忘れられない。特に民主党が政権交代を実現させた後、鳩山総理退陣を受けて成立した菅直人政権の時、「強い経済、強い財政、強い社会保障」というスローガンを打ち出した背景には、神野直彦先生が責任者となって民主党政権の税制専門家会議の座長としてリーダーシップを発揮していただいたことも忘れることはできない。
■ 混迷の日本財政を切り開く憂国の書、新自由主義からの脱出への道を照らす
さて、著書の中身について要約してみたい。日本の財政が抱える課題は深刻であり、どう改革できるのだろうか。最近の国会論議では、財政赤字をどうするのか、基礎的財政収支黒字化目標(=2025年度)も消えかかっている。そんな時、財政学の泰斗である神野直彦東大名誉教授が、渾身の力を込めて書かれたのがこの『財政と民主主義』であり、副題として「人間が信頼し合える社会へ」とある。
神野先生にとっては、戦後の福祉国家から1980年頃から始まる新自由主義への大転換が、「小さな政府=財政支出の削減」となってアメリカやイギリスそして日本を襲い、人々の連帯を根底から破壊し格差社会をもたらしたと批判される。その帰結がリーマンショックであり、新自由主義による小さな政府=小さな財政がもたらしたもので、再び財政の果たす役割が重要という見方が広がり始めている。
財政は民主主義でコントロールされるべきなのに、今や米英日といった新自由主義を取り入れた国では民主主義が機能不全に陥っていると強く警告される。さらに、地球規模でも温暖化やコロナパンデミックなど「根源的危機の時代」が襲っており、どう解決していけるのか、主権国家にとって実に深刻な課題にも直面している。
■ 岸田政権「新しい資本主義」、時代錯誤の重商主義、再分配に触れず
こうした中で、人間主体の経済システムをどう作り上げていけるのか、スウェーデンのロベーン内閣の提起した最新の高齢者ケアと育児のレベルアップした「強い社会」の提起を取り上げる。他方、これと対照的に岸田内閣の「新しい資本主義」についての批判が展開される。岸田総理の提起は、確かに新自由主義批判の言葉はあるものの、「人間」を手段化した時代錯誤の「重商主義路線」に舞い戻り、生活(社会)よりも生産(経済)を重視したものになっている。
また、知識社会のインフラとしての教育の重要性や地方自治体による対人社会サービスの充実が必要なのであり、そのために必要な財源の確保は再分配としての税・社会保険料の重要性を指摘されている。もはや、国会の場ではだれも税を含む公的拠出(負担)の増加が必要であるとは言わなくなっており、再分配政策の重要性の指摘は現役政治家たちにとりわけ重く突き刺さる。
特に、重化学工業からサービス・知識集約産業化が進む中、女性の社会進出による帰属所得(家事労働など)の喪失が起き、社会保険中心では生活保障が困難になる。かくして「社会保険国家」から「社会サービス国家」への転換が求められるのに、それを支える日本の公的負担の低さ、とりわけ租税負担は実に貧弱でしかない。ポスト福祉国家における育児や高齢者ケアといった生活保障の現物給付や、再訓練・再教育を含む教育サービスなどの充実にむけて、所得や消費といったフローの税制だけでなくストックである資産に対する富裕税の新設を提起されている。
■ 基礎的自治体から始まるヨーロッパや日本の新しい自治体作りとデモクラシー
さらに、大量生産・大量消費社会という「量」から、存在欲求を充足する「質」を重視した経済・社会が求められる時代になっていることを指摘され、具体的にフランスのストラスブールやドイツのルール地方の街づくり、日本での大正デモクラシー以来続いている三重県度会郡七保村や信州における教育国民運動などの基礎的自治体レベルの取り組みにも言及されている。
さらに、大変重要な財政の課題として、民主主義を危うくする「巨大な富の形成を阻止する」ことの重大性を指摘され、資産課税の強化を取り上げ、戦後のシャウプ税制で一度失敗した富裕税の導入の必要性にも言及されている。
■ 故宇沢弘文東大名誉教授の神野先生に贈られた「ことば」、根源的危機の時代とどう立ち向かうべきなのか
最後に、神野先生に対する故宇沢弘文名誉教授の贈られた言葉が紹介されている。神野先生は、これを「私に下された『垂訓』である」と受け止めておられる。
「未来へのシナリオは、単に未来を現在の延長として予測するのではなく、人間を人間として充実させるビジョンとして描かなければならない」(宇沢弘文「リベラリズムの立場に立った真の意味における経済学者――神野直彦氏の人と業績」『自由思想』2003年12月号)
これに対する神野先生の言葉が最後のページに次のように書かれている。
「私たちは、週末的破局を恐怖してはならない。恐怖すべきは『人間を人間として充実させる』希望のビジョンを描く意欲を阻喪してしまうことである。『人間を人間として充実させる』未来へのシナリオを描き、希望を胸に、意志の楽観主義にもとづいた努力を重ねることが、『根源的危機の時代』に生を受けた私たちの責任なのである」(244頁)
この本を読み終えながら、ふと神野先生が語っておられた言葉を想いだしていた。それは、東京大学経済学部の大内兵衛教授以来築かれて来た伝統あるドイツ財政学講座が、神野先生でもって終わるのだ、という趣旨の言葉だったと記憶する。この著書はそうしたドイツ財政学に命を懸けてこられた神野先生の心からの叫びが凝縮されたものになっているように思えてならない。
(注 この第515号は、3月24日に発刊された同人誌『メディアウオッチ100』第1778号に寄稿した「1冊の本」というコーナーに出した原文を補強して掲載したものである)