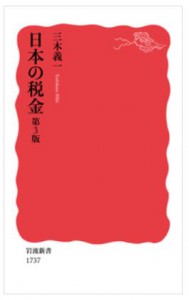金子宏先生、文化勲章受章おめでとうございます!
今年度文化勲章を受章した金子宏先生(東京大学名誉教授)は、私たちの国際連帯税活動をずっと“熱く”支援してくれています。先生と国際連帯税との繋がりをふり返ってみました。
実は金子先生には、これまで2度実際に講演等を行ってくれています。そもそもどうして私たちが金子先生を知ったのかと言いますと、2006年8月3日のことですが、日本経済新聞のコラム経済教室に「人道支援の税制創設を 国際運輸に定率で」と題した論考が載ったことが契機でした(下記参照)。「あっ、何と租税法のオーソリティーが連帯税を提唱している」とたいへん驚き、それで先生に連絡を取ったのでした。
この頃はまだ国際連帯税議員連盟もなく、また外務省や財務省に行ってもまともに相手にされず、国際連帯税はNGOや研究者の活動に留まっていました。ですから、これだけのオーソリティーがほぼ連帯税の考え方と同じ人道税を提唱したことに大いに鼓舞されたことを覚えています。
ともあれ第1回目の講演は、2007年1月12日にグローバル・タックス研究会(*)の場で行っていただきました。そのもようはこちらご覧ください(なお、講演内容はオルタモンドのWebサイトを通してPDF化していましたが、このWebがなくなったため消えてしまいました、残念)。
(*)同研究会は、NGOオルタモンドと当時上村先生が赴任していた千葉大地球福祉研究センターが中心となって行われたものです。
第2回目の講演は、2008年11月22日に開催した「『国際連帯税』東京シンポジウム2008」の 「専門家会合」で“各連帯税・資金メカニズムに関する提言”セッションで行っていただきました。
また、講演のほかに、2009年10月には「国際航空券税(国際人道税)等国際課税の問題について」と題するIMF財政局税制担当課長との公開会談を行っています。ここで先生は、先の日経記事の内容をさらに深めています。
そして先生の連帯税に関するもっとも大きな仕事は、2010年9月政府税制調査会の専門家委員会 に設置された国際課税小委員会の第1回目に特別報告を行ったことです。この小委員会の設置については、当時の政府税制調査会を仕切っていた峰崎直樹財務副大臣の並みならぬ努力があったと聞いています。
先生の政府税制調査会に提出された資料はここから見ることができます。その中に日経新聞に載った「人道支援の税制創設を 国際運輸に定率で」も入っています。
この年は、日本政府が革新的資金調達に関するリーディング・グループ(国際連帯税等を推進したい各国政府の集まり)の議長国になり東京で大規模な総会が開催され、また政府税調でも国際連帯税をメインのひとつとした国際課税小委員会が設置され議論するなど、もっとも連帯税実現に近づいた年でした。しかし、同年ナショナル・フラッグであった日本航空(JAL)が倒産し、また全日空(ANA)も空前の赤字に転落するなど、航空業界を取り巻く経済状況が最悪という状況でした。こうした状況もあり、国際連帯税の第一弾となる(はずの)航空券連帯税は、結果として見送られてしまいました。
ところで、金子先生は1930年11月生まれですので、この年ちょうど80歳となられました。その後は外での講演などは控えられましたが、私たちは日本リザルツの白須代表がことあるごとに先生に連絡し、助言をいただいていました。そしてみなさんもご存じのように、本年7月26日開催した「SDGsのための国際貢献と国際連帯税を考えるシンポジウム」にも激励のコメントを寄せてくださりました。
以上から分かりますように、金子先生は租税法のオーソリティーでありますが、決して学問や法解釈の世界に閉じこもっていたのではありません。途上国の紛争や貧困・飢餓、とくに子供たちの苦しみに胸を痛め、その救援のための方法として税制の面からアプローチを試みたという点で、まさに実践家でもありました。門下生はもとより先生の教えに学んだ学生は数知れず、そしてかなりの人が政財官の中枢を担っていると思いますが、ぜひとも先生の国際人道税構想を忘れてほしくないと思います。
最後に金子先生の教えです。「国際航空旅行は国外における消費行為であるから、国家の課税権はこれに及ばないのではないか、という批判がありうるが、国際航空券税は、 国際社会が課税権をもっている消費行為に対して、国際社会がまだ徴税機構を持つほどに組織化されていないため、各国家が国際社会に代わって徴収し その税収を国際機関に転送する仕組みであると考えるのが、グローバリゼーションの時代に適合しているといえる」(「人道支援の税制創設を」)。しかし、今次の国際観光旅客税は日本が(勝手に)自分たちだけのために使っているという点で、本来国際社会の税収とすべきものに対する課税権の越権行為と言えましょう。