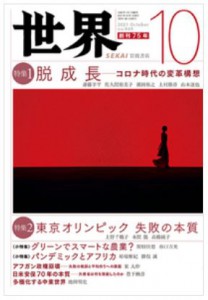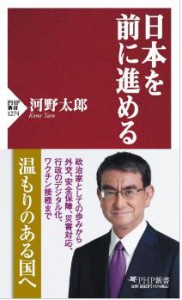●いっそう拡大する高所得国と低所得国とのワクチン格差
WHOは4日、コロナワクチンの3回目の接種につき、低所得国等でワクチン不足から9月末まで中止すべきと見解を出しました。実際、人口1人当たりのワクチン購入量は、カナダ10回強、英国8回などですが、アフリカ連合はわずか0.36回という状況です(8月5日付日経新聞)。しかし、高所得国はWHOの見解に構わず接種を行おうとしています。
低所得国などの支援への圧倒的な資金不足と特許の壁がグローバルなワクチン格差を招いています。前者の役割を担おうというのが国際連帯税であり、その実現が望まれるところです。
●国際連帯税に関するアンケートの結果
さて、先日「国際連帯税に関するアンケート」をお願いしたところ、386人からのアクセスがありまして、具体的な回答を38人の方からいただきました。まことにありがとうございます。みなさまの貴重なご意見、アイデアについては今後の国際連帯税活動の参考にさせていただきます。
なお、今回アンケート結果を第1回としたのは、これからもどしどしアンケートを実施し、みなさんのご意見等を聞いていこうと思っています。以下、結果についてご報告しますので、よろしくお願いします。
【Q1】国際連帯税に賛成ですか?
・賛成 81.6% ・反対 5.3% ・どちらでもない 13.2%
【Q2】賛成/反対/どちらでもないの理由は?
1)主な賛成理由:
①不勉強なのですが…、気候危機にせよパンデミックにせよ、先進国だけで解決できる問題ではありません。そもそも先進国がその拡大により多くの責任がある事だと思います。先進国のリーダーシップや技術移転、資金援助のような上から目線の対策ではなく、フラットな関係で共に問題に取り組むためには国際連帯税のフレームがいいのではないかと考えました。
②国際間取引には国際的な目的税をかけるのが順当であり、また実態経済とかけはなれた自動高速投機の抑制にもなる。加えて、国境を越えた問題を解決するには国家政府を越えた地球政府機関の独自財源が必要だと考えるため。
③グローバルな問題を解決する上で、ODA資金やその亜種では、国の意向が強く働き過ぎるし、約束した拠出を守らない政府が多数存在するので、資金規模不安定となる。民間資金では利益に直結しにくい分野への投資は期待できない。したがって、旧来の公私の資金に依存しない新しい資金メカニズムが必要であり、国際連帯税はその可能性を有している。
④グローバルな課題の解決において、先進国の国際政治上のその時々の思惑に左右されることなく、持続的に資金が確保できる方策が必要であるため。
⑤炭素税などは国単位でも行っているところがありますが、まだまだグローバルには展開できていないのが現状ですし、為替税でケア階級の人にユニバーサルベーシックインカムを導入する一端を担うことを期待しております。
⑥各国の拠出金だけでは不測の事態に対応できない。実際、コロナ対応ですら失敗の連続だった。近代的な国民国家の枠組みにもそろそろ限界が来たのではないか、と改めて考えさせられた。二十一世紀、今こそ、世界的な視野を持ち、国際的な税の導入をすべきだと思う。
2)主な反対理由:
①意図は賛成できますが,徴収手段の構築が難しいと思います。
②学問的にまだ定まっていないから
③今時期尚早
【Q3】あなたの性別は?
・男性 65.8% ・女性 28.9% ・その他 5.3%
【Q4】あなたの年代は?
・10~20代 7.9% ・30~40代 34.2% ・50~60代 39.5% ・70代以上 18.4%
【Q5】主なアイデア・ご意見について
①賛同するNGO・NPOの世界的合流を通じ、国際連帯税の根拠となる国際条約成立の実現を目指し、取組みをより一層強化する。
②反対の立場に立ち得るステークホルダーの中から理解者や協力者を得て、幅広く捲き込んでいくことが、強硬な反対意見へのプレッシャーになっていく。
③炭素税、武器取引税、感染予防協力税、児童労働税など、SDGs問題解決のための課税を検討する。
④核保有国への核兵器開発を止める平和分担税など、無駄な軍事費を地球環境問題などに活かしていく。それには、核兵器禁止条約を国連加盟国に批准を求める運動を強化していく。
⑤まずは学問的な知見を国内で増やすことが肝要。
⑥中学校の道徳や自由研究、高校で言うところの総合的な学習に取り上げられるレベルを目指す。
⑦アイデアとしては、若者に訴え、世論を動かす為には、国際連帯税についてYouTubeなどに投稿する。
⑧まずは、先般(7/9~10)イタリア・ベネチアでの財相・中央銀行総裁会議(G20)合意を最終化するよう、日本政府に働きかける。合わせて法人最低税率引き上げ導入方策などさらなる国際課税ルールづくりのため、「国際連帯税創設を求める議員連盟」などにも具体的に提案し、働きかける。
⑨地方自治体からの請願を組織的に行う。国際的なネットワークを強化し、G7やG20の議題に取り上げるように働きかける。ダボス会議の活用も考慮する。
⑩ 国際連帯ってあまりにも抽象的なのでパンデミック対策税とかネーミングを工夫したらどうでしょうか?
⑪具体的に何に誰が課税する、あるいは使途はどのように決めるのか、また懸念されること、反対の立場の人たちの主張など、具体的な議論があれば、関連した議論が考えやすいものになると思います。
⑫今回のG20決議を踏まえて、国内の議論形成の場を早急に作る。