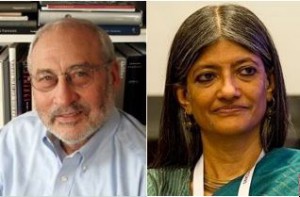今週の日曜日(1/31)のTBSサンデーモーニングで、新型コロナウイルス(以下、コロナと略)のワクチン問題を特集として放映していましたが、コメンテーターの松原耕二氏が「ワクチンの(世界的な)争奪戦を見ていると、芥川龍之介の小説『蜘蛛の糸』(*)を思い出す。まず豊かな国々が我先にと糸にぶら下がり、でも貧しい国は糸につかまることすらできていない」、と。テレビでは、イスラエルがどんどんワクチン接種をしているのに、すぐ隣のパレスチナ系住民は一人も接種していない模様も放映されてました。
(*)超大まかあらすじ:お釈迦様が地獄にいる亡者の一人を助けようと極楽から糸を降ろすと、その亡者がその糸を手繰って上ってきたが、ふと下を見ると多くの亡者がその糸にしがみつき上ってきている。そこでくだんの亡者が亡者たちを振り落とそうとし、「これは俺のものだ」と叫んだとたん、ぷっつりと糸が切れて亡者は真っ逆さまに地獄に落ちていった。
●コロナワクチンを富裕国が囲い込む
コロナがパンデミックとなってから1年が過ぎ、世界で感染者がついに1億人を超え、死者も200万人を超える事態となっていますが、その脅威は未だ衰えるところを知りません。コロナ感染を防止するための強力なツールのひとつがワクチンです。これが異例のスピードで開発され、各国で接種がはじまりつつあります。
ところが、まだワクチンの供給が十分ではないのに争奪戦となり、富裕国がほとんどを確保してしまう有様となっています。国際NGOオックスファムによると「人口の約5倍のワクチンを調達するカナダを筆頭に先進国の多くが人口の約3倍の確保を予定し、低・中所得国では2021年末までに人口の10%未満しかワクチンを接種できない可能性となっている」と報告しています。また、英誌エコノミスト系の調査部門の報道によりますと、途上国にワクチンが行き渡るのは2023年以降にずれ込む見通し、とも報じられています(1月31日付日経新聞)。
●本来COVAX(コバックス)が富裕国・貧困国別なく公平に配布するはずが
国際社会は、昨年WHO(世界保健機関)の呼びかけで、医療体制が脆弱な低所得国等を支援するために「ACTアクセラレーター(Access to COVID-19 Tools Accelerator)」を設立し、ワクチン・治療・診断・保健システムという4つの柱を軸に対策を進めています。そのうちのワクチン関係を担っているのが「COVAX(COVID-19 Vaccines Global Access)ファシリティー」です。
COVAXは富裕国の資金でワクチンを共同購入し、途上国にも公平に配布しようというファシリティで、現在190か国が参加しています。が、当初ワクチン大国の米国、中国、ロシアが不参加でしたので、最初から資金不足に見舞われ、目標も2021年末までに途上国に20億回分のワクチン供給を目指すというものでした(その後米国、中国が参加することに)。
今年に入り、COVAXは92カ国に供給し、対象国の総人口の約27%への接種が可能という見込みを立てました。しかし、先進国を先頭に多くの国がワクチン保有国や製薬会社と個別に交渉し、ワクチン確保に躍起となってしまいました。このためCOVAXに参加している多くの途上国ではワクチンの確保や接種開始のめどが立たない状態となっています。
●国際社会が共同して拠出する国際連帯税方式で支援を
こうした憂うべき状況をもたらしている要因として、1)国際的な政治的リーダーの不在、2)COVAXを含むACTアクセラレーターへの資金の圧倒的不足、ということが挙げられます。
その資金不足ですが、ACTアクセラレーターの第3回会合で、「(昨年)12月14日時点で、今後数か月の緊急需要のための資金ギャップは43億ドルであり、2021年には追加で239億ドル(約2.6兆円)が必要」と試算されました。ところで、資金調達のためには、(いぜんとして)各国のODA予算からの拠出が主力となりますが、そろそろ国際社会は国単位でのバラバラな資金拠出方式から、共同して資金調達を行う仕組みを構築することが必要ではないでしょうか。
その理由の一つは、ドナー国となる各国も国内のコロナ対策のために多大な借金政策をしており、ODAを増加させる余力がまったくなくなっていること、もう一つはグローバル化によってばく大に儲かっている経済セクターから税またはフィー(料金)を徴収する仕組みを考える時期に来ていること、です。後者についてですが、国境を超える活動に対して税を課す国際連帯税方式で、外国為替取引やデジタル商取引等に適用できるでしょう。ちなみに、世界の為替取引量は2019年で年間約1647.5兆ドル(18.1 京円)にも上っています。ここに薄い税、例えば0.005%をかけるのです。すると9兆円の税収を得ることでき、ACTアクセラレーターの必要資金を優に賄うことができます。
政治的リーダーで言えば、かつて2004年当時シラク仏大統領がルーラ伯大統領とともに国際連帯税創設を国際社会に訴え、近年で言えばつい一昨年まで河野太郎外務相が国際連帯税の共同実施を国際会議の場で提案していました。現在どの国の政治リーダーも国内のコロナ対策で手一杯という状況にありますが、国連ならびにG7やG20サミットの場で、どこかの首脳が国際連帯税を提案することを期待します。そのような結束と資金提供がなければ、ワクチンを外交の道具に使おうという大国の跳梁を許すことになります。
●途上国を取り残してのコロナ対策は次のパンデミックを招くだけ
コロナ禍が「経済格差」をいっそう浮き彫りにしたと言われますが、このワクチン争奪戦での富裕国の一方的なワクチン確保状況を見ますと、グローバルな規模での「格差」を示していると言えます。こうした状況は「誰一人取り残さない」というSDGs理念に真っ向から反するものです。
そして、何よりも途上国を取り残してのコロナ対策は、グローバル化が進んだ今日、再びパンデミックを招くことになり、先進国の努力も水泡に帰する可能性が大きいと言えます。あらためて先進国の政治リーダーは目先の、足元だけの対策だけではなく、並行して中長期の、地球規模の対策を考えていただきたいと思います。
ところで、日本政府の態度はいかなるものでしょうか。昨年12月に行われた国連新型コロナ特別総会にで菅首相は次のように述べています。「日本は、その(ACTアクセラレータの)共同提案国として、ワクチンの公平なアクセスのためにCOVAXファシリティに、いち早く拠出するとともに、特許プールを通じた治療薬の供給などに取り組んでいきます」。
その言や良しですが、現実は日本もやはり外国産ワクチン確保の争奪戦にのめり込んでおり、途上国に対しての思いやりは二の次となっています。国際的な発言ができる首相はじめ、外務相や財務相が国連、そしてG’7やG20サミットの場において、ワクチンの公平な流通とACTアクセラレータへの資金調達のため共同して国際連帯税を創設しようと呼びかけることが期待されます。