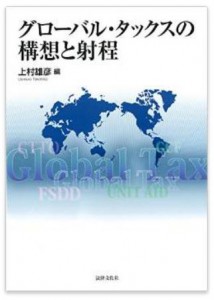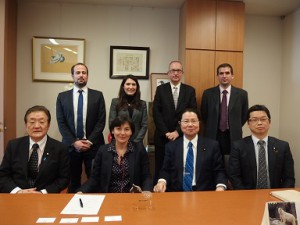今日は「子どもの日」ですが、各新聞の社説を見ると、「子どもの貧困」を取り上げている新聞が多いですね。子どもの貧困についてはここ数年問題となってきましたが、昨年厚生労働省は2013年の「国民生活基礎調査」で子どもの貧困率が16.3%に達し(2012年段階)、過去最悪となったことを公表しました。
実際、「学校現場では、給食以外満足な食事を得られない子や、医療費を負担できず病院に行けない子も報告されている。放置すれば社会の階層化と格差拡大が進み、子供が将来に希望を持ちにくい社会となりかねない」(14年7月20日付毎日新聞)という懸念が一層拡大してきています。
子どもの将来に希望を持ちにくい国というのは、その国の将来に希望を持ちにくいということを物語っています。このままでは少子化とともに確実に衰退していくでしょう。いずれにせよ祝日である子どもの日に子どもの貧困を考えなければならないというのは国として恥ですね。
ところで、その対策ですが、「国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩・社会保障応用分析研究部長は『子どもの貧困率は景気がよい期間も上昇傾向が続き、景気対策だけで解決しないのは明らか。教育などを充実させるだけでは不十分。現金給付を増やし、生活苦を和らげて初めて、教育の充実も有効に機能する』と強調」(同上)しています。まさに「税制や社会保障政策の出番」(朝日新聞・社説)ですね。
ともあれ、各マスコミの社説を要旨とともに紹介しますが、全文についてもぜひお読みください。
2015年5月5日(火)付 朝日新聞
日本の子どもの今を考えるとき、見過ごせない数字がある。16・3%。子どもの貧困率である。ひとり親など大人が1人だけの世帯の貧困率は、5割を超える。先進国の中で最も高い水準だ。
親を亡くした子どもたちを支援する「あしなが育英会」が、奨学金を受けている高校生にアンケートをしたところ、こんな声が寄せられた。「正直あした食べるご飯に困っている。早く自立できたらと何度もふさぎこんだ」「学校では食べずにガマンしている。友達といるとお金がかかるのでいつも一人でいる」
■不十分な政府の対策
安倍政権は子どもの貧困対策法の成立を受け、総合的な対策を進める大綱を昨年、決めた。しかし、ひとり親家庭への児童扶養手当を増やすことは、財源不足などを理由に見送られた。また、子どもの貧困率を下げる数値目標もない。
…不平等をなくすのは政府の役割だ。「国民全体で負担し、支え合う」という、税制や社会保障政策の出番である。その意味で疑問を感じるのが贈与税の非課税枠の拡大だ。…ゆとりのある家庭には恩恵が大きいが、家庭間の不平等を広げかねない危うさをはらむ。
■おせっかいの勧め
■支える連鎖を生もう
大人が関わることで、子どもを支える連鎖も生まれる。…奨学金を受けてきた大学生たちも、支援活動に加わっている。民間団体の有志らが集まり政策を提言する「子どもの貧困対策センター」。その設立に向けた募金活動を5日に行う。
…少しだけ、おせっかいになってみよう。大人になっても貧困から抜け出せない「貧困の連鎖」を断ち切ることにつながるかもしれないのだから。
2015/5/5付 日本経済新聞
「団塊の世代」が生まれてすぐの65年前には3人に1人だった。30年前には5人に1人、そして今では8人に1人――。日本の総人口に占める14歳以下の子どもの割合だ。…子どもを持つかどうかは、もちろん個人の選択だ。しかし子どもを持ちたいと望んでも、それを阻む様々な壁がある。社会全体で子育てを支え、子どもが健やかに成長する環境を整えたい。
妊娠中からきめ細かく
…子育てや子どもを支える施策には、一定の費用がかかる。20年までの少子化対策をまとめた大綱は、財源を確保して予算を増やすとしたが、具体的な手立ては盛り込まなかった。子どもの貧困対策として、政府は夏までにひとり親家庭や子どもが多い家庭への支援策をまとめる予定だ。この財源もどう手当てするのか。どんな施策を優先させるのかを含め、議論を深めなければならない。
一人ひとりが担い手に
…多くの大人が活動にかかわることで、子育て家庭の負担は軽くなる。参加する人にとっても生きがいになる。かつて支援を受けた人が、やがて支援をする側に回るという好循環も期待できる。少子化がこのまま進めば、日本経済は活力を失い、社会保障制度の土台も揺るぎかねない。行政も私たち一人ひとりも、前に踏み出すときだ。
2015年05月05日 京都新聞
<けなされて育つと、子どもは、人をけなすようになる>で始まる詩をご存じの方も多いだろう。米国の教育学者ドロシー・ロー・ノルト博士の「子は親の鏡」だ。…この詩を基にした博士の著書「子どもが育つ魔法の言葉」(PHP文庫)は世界中で愛読され、日本でも120万部を超すベストセラーとなった。…通底するのは子どもとしっかりと向き合うことの大切さだ。親は心にゆとりが求められる。だが、今の日本には生きていくのに精一杯で、わが子と向き合う余裕のない家庭が少なくない。
支援の手を緩めるな
…とりわけ母子家庭は深刻だ。子どもを抱えての就労が難しく、4割以上は非正規雇用で平均就労年収は200万円に満たない。子どもの貧困率は5割に跳ね上がる。貧困には負の連鎖も付きまとう。生活苦で進学を諦め、大人になっても安定収入を得られる職に就けず、貧困にあえぐ。その子どもも同じ境遇を繰り返す。生活保護受給世帯で育った子どもの4人に1人が大人になって再び生活保護を受ける、との調査結果もある。
深刻さ増す児童虐待
ネットの危うさ懸念
…冒頭の詩は<和気あいあいとした家庭で育てば、子どもは、この世の中はいいところだと思えるようになる>と結ばれている。
2015年5月5日琉球新報
今日は「こどもの日」。沖縄の未来を担う子どもたちの幸福や教育のため、予算や労力は惜しみなくつぎ込むべきだと強調したい。…県民所得が全国最下位にある沖縄は、もっと深刻だ。特に厳しい状況にある「ひとり親世帯」の割合は、沖縄は全国の約2倍。県のひとり親世帯の実態調査では、生活状況が「苦しい」と回答したのは13年度で8割に上り、母子世帯に比べ余裕があるとされた父子世帯の環境悪化が目立った。
…使途をめぐって議論がある一括交付金などで、子どもを毎年百人、いや千人規模で留学させるような発想があってもよい。そのくらいの大胆さで、教育には予算をつぎ込むべきだ。
子どもの貧困は、食事や栄養などの「健康格差」にも直結しているとの非常に気掛かりな指摘もある。子どもたちを取り巻く課題の解決は、社会全体に課せられた課題であることを再認識したい。その取り組みは待ったなしだ。